あなたの遺言お届けします
『人の死』には幾つか種類がありますが、死者のほとんどは無慈悲にもある日突然前触れもなく日常と切り離されてしまうものです。
そう、糸が切れるようにプツンとね。
そうして死にゆく者のすべてが自分の遺志を伝えたい人に伝えることができるというわけではありません。それは長年連れ添った伴侶への愛や感謝を込めた言葉であったり、遺される家族への慰めや励ましでもあったりするでしょう。または、それとは反対に怨嗟に満ち溢れた場合もあるのではないでしょうか。
今回はそういった類い稀な事案をひとつご紹介させていただこうと思います。~Present by YUIGON Mail Service~
「遺言…?」
私は差し出されたスマートフォンの画面を信じられない気持ちで見ていた。鯨幕を彷彿とさせる白と黒の縦縞模様を基調としたスクリーンには流れるように美麗な文字で【遺言メールサービス】と表示されている。その文字の下には小さな遺影よろしく黒い額縁に納められた【差出人】の顔写真と、氏名と享年が記されていた。
「これって…」少し混乱気味に呟くと、向かいの席からあっけらかんとした声が聞こえた。
「笑っちゃうでしょ?あの義母の最後のい・や・が・ら・せ。」
兄の妻であり義理の姉でもある彼女が腰掛けた椅子から身を乗りだして眉をしかめてみせた。そのおどけたような振る舞いの裏に隠された怯えを麻衣子は見逃さなかった。
「それで…なんて書いてあったの?この、遺言?メールには。」義姉の性格からして真偽不明なメールを開くというリスクは決して犯さないだろうと思いつつ、一応は尋ねてみた。
「まっさか~。麻衣ちゃんならこんな怪しさ100%のメールを開けちゃうのぉ?」と、義姉の梨香はケラケラと笑い声をあげた。
「どうせ怨み言しか書いてないわよ、あの婆さん。くたばる前の日まで文句たらたらだったんだから。」
そう言うと、思い出すのも嫌だという風に片手をひらひらと振ってみせる。生前の母と義姉の不仲は親族を含めた多くの知人が知るところだった。
「どうやっても消去出来ないのよね、これ。電源を落としても再起動してもダメなのよ~。生きてても死んでても本当にしつこいんだから。」
母と義姉は家の中であろうが人前であろうがお構い無しに激しい口喧嘩をよくしていた。それこそ血の繋がった実の母子のように、どちらもまったく遠慮なんてしない間柄だったのだ。そんなふうに言いたいことを言い合える関係を築くのは引っ込み思案な麻衣子には難しくて、ほんの少しだけ二人を羨ましいと思っていた。
───いや、正直に言ってしまえば妬ましかったのだと思う…
─────母を手にかけてしまうほどに。
「まあ冗談はさておき、詐欺とかウイルスだったら怖いじゃない。変に弄くるよりも専門家にお願いした方が間違いないでしょ?」
「義姉さんったら…専門家なんてやめてよね。」携帯電話ショップの販売員として働いている麻衣子は思わず吹き出してしまった。まぁ確かにこの店舗では古参に違いないけど。
結局【遺言メールサービス】とやらを端末ごと放棄することに決めた義姉は、さして迷うこともなく発売されたばかりの新しいスマートフォンを購入してご機嫌だった。蓄積されたデータに頓着しない性格も亡き母とよく似ていたのだと麻衣子は今さらながら思い知らされる。そして古い端末はその場ですべてのデータを初期化されてガラクタと化し役目を終えた。
「開いてみれば良かったのに。もしかしたら今までのお礼とか謝罪が書き連ねてあったのかも知れないじゃない?」
手続きを進めながらさりげなく促してみると、義姉はぶんぶんと勢いよく首を振ってから答えた。
「いいのよこれで。仲の悪い嫁と姑で何不自由なく何年も一緒に暮らしてたんだもの。…今さらずけずけ言い合える相手が居なくなって寂しいなんて…お義母さんにも誰にも知られたくないし。だからこれでいいの。」
そう言って義姉は瞬いた。
…本当に憎たらしい女だこと。お前もじきに母と同じところに送ってやる…
その日の勤務を終えて帰宅した麻衣子は自宅の郵便ポストから【遺言メール便】を取り出した。【差出人】の欄には当然のように母の名が記されている。薄墨色の紙で丁寧に包まれた小さなその箱を無造作にごみ箱に投げ棄ててから麻衣子は思案する。次はきっと【遺言宅配便】が届くのだろう、と。
何のことはない…義姉の仕組んだ罠だったのだ。私の反応を直接探りに来たのが何よりの証拠だろう。───確かに…転倒事故に見せかけて母を階段から突き落としたのは私だ。だけど義姉さん?階段の踊り場と手摺をツルツルに磨きあげていたのは…いったい誰?
未必の故意だったかしら…?ふふ、義姉さんもやるじゃない。にやにやと歪んだ笑みを噛み潰しながらリビングの電気をつけるとそこに母が居た。
無様に尻餅をついた麻衣子の視線の先には生前と同じように背中を丸めて正座している母の背中があり、正面の掃き出し窓にはガラスの反射越しに麻衣子を見つめる能面のような母の表情がはっきりと見てとれた。
───あんたがなかなか遺言を受け取らないからここまで来ちまったよ───ぼそりと囁くような母の声が脳内に届いたその瞬間、麻衣子は白目を剥いて意識を失った。泡も吹いたし、なんならパンツもびしょ濡れになった。
えっ?自首するって?
そうかい。…それより二階の押し入れの左側の天袋の奥の隅に昔お父さんにもらった手紙の束と五百円玉を貯めてたクッキー缶が隠してあってね…
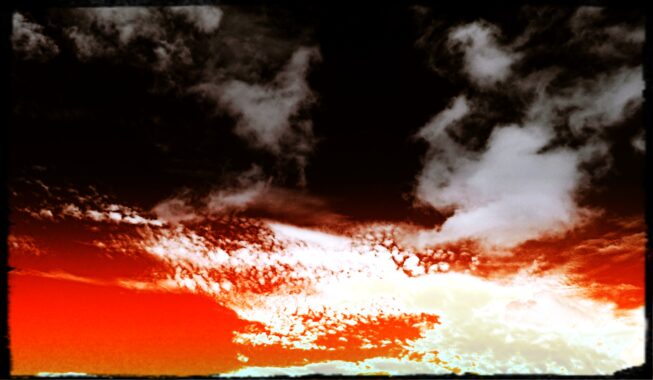










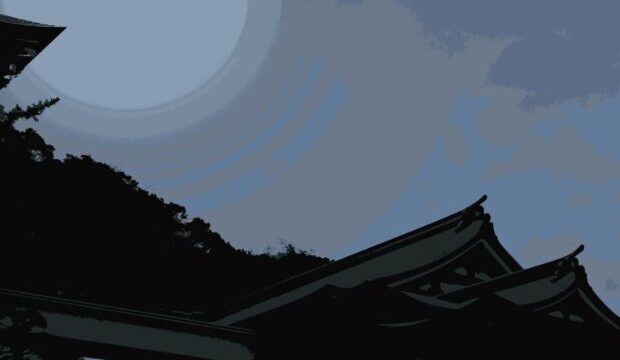
















コメント